情報過多の時代に求められる「思考の拠点」
スマートフォン、Slack、Notion、Googleドキュメント、ChatGPT──
気づけば、私たちの周囲には「情報」が溢れ、1日に触れるテキスト量は数万単語を超えています。
特にプロダクトマネージャーやクリエイター、研究職のような知的労働者にとっては、インプットとアウトプットを高速で繰り返す「思考の筋トレ」が日常です。しかし、同時にこんな悩みも増えています。
- あのメモ、どこに書いたっけ?
- 思考が断片化してしまう…
- アイデアが蓄積されず、毎回ゼロから考えている
こうした「思考の散逸」を解消し、脳の外部ストレージとして機能するのが、ObsidianとCursorの組み合わせです。
Obsidianとは何か?なぜ「今」使うべきか
Obsidianは、一言で言えば**「リンク可能な思考のためのノートアプリ」**です。
マークダウンで書けるメモをローカルに保存し、ノード同士を双方向リンクでつなぐことで、まるで自分だけのWikipediaのような“知識のネットワーク”を構築できます。
特に注目すべきは以下の点です:
- 完全ローカル保存で高速かつ安全
- [[リンク]]や#タグによる情報の接続
- Graph View(知識マップ)で思考の全体像を可視化
この構造化メモは、従来の「階層フォルダ型」のノート管理とは全く異なり、思考の流れに沿って、自由に知識を編み上げていけるという点で非常に優れています。
Cursorとは何か?なぜAIエディタが「思考」を助けるのか
CursorはAI搭載のコードエディタとして知られていますが、実はドキュメント執筆、メモ編集、思考のサポートといった知的作業にも非常に強力なツールです。
- GPT-4/GPT-4oを活用した自然な補完
- 選択テキストへの対話型プロンプト
- コード、文章、構造の理解に強く、全体の整合性も取れる
たとえば、
- 思考の断片を自然言語で書き出す
- Cursorで「要約して」「論点を整理して」「この流れで続きを書いて」と頼む
- その結果をObsidianに蓄積し、次の議論や企画に活かす
このように、人間の思考に並走するAIアシスタントとしてCursorは今、進化を遂げています。
ObsidianとCursor、それぞれの強みをどう活かすか
- Obsidian → 情報の「保存」「接続」「再利用」が得意
- Cursor → 情報の「生成」「変換」「対話型編集」が得意
この2つを組み合わせることで、“思考の蓄積”と“再利用可能なナレッジ化”が同時に実現するのです。
知的生産のワークフローをどう設計するか
〜ObsidianとCursorを軸にした“思考の循環”モデル〜
前章で、ObsidianとCursorそれぞれの役割と可能性を整理しました。ここからは、この2つをどう組み合わせ、日常の仕事や思考に組み込むかについて掘り下げていきます。
ステップ1:思考の「受け皿」を作る(Obsidian)
まず必要なのは、思考のすべてを“とりあえず受け止める”受け皿です。ここで活躍するのがObsidianです。
■ デイリーノート活用のススメ
Obsidianには「デイリーノート」という機能があり、毎日の思考・ログ・メモを1ファイルにまとめられます。
たとえば次のように活用します:
# 2025-05-24
## 📌 Today’s Focus
- 企画Aの構成作成
- ミーティングメモの整理
## 🧠 思考メモ
- “蓄積される環境”が生産性の鍵になってきた
- ObsidianでのアウトラインとCursorでの詳細執筆の使い分けが重要かも
## 🗒 Memo
- チームメンバーXとの会話で気づいたこと:...このように、雑多な情報もまずはここに投げ込んでおくことで、情報を「溜める」場所が生まれ、後で活用しやすくなります。
ステップ2:構造化する(リンクとタグ)
デイリーノートに記録された情報は、必要に応じて他のノートにリンクしたり、タグで分類していきます。
[[思考術/Obsidian活用]]#アイデアストック[[プロジェクト/企画A]]
こうすることで、一度書いたアイデアが孤立せず、文脈ごとに再利用される仕組みができます。これはNotionやGoogle Docsにはない、Obsidian特有の“知識が育つ感覚”につながります。
ステップ3:Cursorで「深掘り」する
思考の断片やアイデアが溜まったら、次はCursorの出番です。
使い方の一例:
- Obsidianで書いた思考メモをそのままコピーしてCursorに貼る
- 任意の箇所を選択し、右クリック → 「AIに聞く」
- 「このアイデアを3つの視点から展開して」
- 「この流れに合う導入文を追加して」
- AIが生成した文章を参考にしながら、自分で再構成・編集
このプロセスを通じて、ぼんやりした思考が明確な文章・企画案へと変換されていきます。
ステップ4:再びObsidianに戻す
Cursorで整えたテキストは、再びObsidianに戻して保存・リンクします。
- たとえば
[[企画A/構成案]]として保存し、今後の会議や実装フェーズで再利用 [[アイデアストック]]にリンクを貼って、今後のネタとして活用
このように、ObsidianとCursorの間を“思考の素材”が行き来することで、思考の「循環サイクル」が完成します。
このワークフローが生むもの
- 書くことが苦手でも、AIが補完してくれるので迷いが減る
- 情報を溜めて→整理して→展開して→また蓄積するという循環が生まれる
- 結果として、思考の質と再現性が高まる
このワークフローを日々回すだけで、蓄積される知的資産は圧倒的な差を生みます。
プロダクトマネージャーの1日に見る、Obsidian×Cursorの実践例
〜“情報の洪水”を味方に変えるワークスタイル〜
プロダクトマネージャー(PM)は、社内外の多様な関係者と連携しながら、要件定義、企画立案、仕様調整、スケジュール管理、そして未来の方向性までを担う“全方位型”の職種です。
そのため、日々次のような作業が発生します:
- 会議での議事録作成や決定事項の整理
- ユーザーや顧客の声の収集・構造化
- アイデアのブレスト、資料化
- 技術やビジネス要素の調査と理解
- チーム間のコミュニケーションとフィードバック
この膨大な情報を、ただ“処理するだけ”では差がつきません。いかに「思考を資産化」していけるかが、経験年数に比例しない成果を生む鍵となります。
ここでは、あるPMの1日を例に、Obsidian×Cursorの活用プロセスを見ていきましょう。
8:30|出勤 & Obsidianで「今日のテーマ」整理
始業前にObsidianのデイリーノートを開き、前日のログをざっと見返してから、今日の主な目的を設定します。
# 2025-05-24
## 🎯 今日のテーマ
- ユーザーインタビューのフィードバックまとめ
- リニューアル案のコンセプトを明文化
[[ユーザーインタビュー/5月実施分]] → ここにまとめていく
[[リニューアル構想/Ver3]] → 企画案として発展この段階では、未整理でもOK。「何に集中すべきか」が明文化されるだけで、日中の迷いが減ります。
10:00|インタビュー実施 & その場でObsidianに記録
Zoomなどでのインタビュー中、リアルタイムにメモをObsidianに記録します。
# ユーザーインタビュー/5月実施分
## 👤 A社マネージャー
- 毎回プロジェクトが「ゼロベース」で、過去の知見が活かしにくい
- 複数人で同時に仕様を把握・共有できる環境が欲しい
→ [[課題分析/属人化]] にリンクキーワードにリンクを付けながらメモしておけば、後で構造的な整理もしやすくなります。
13:00|Cursorで「構想案」を起草
午後は、午前中に得た気づきから、リニューアル構想案のベースをCursorで書き始めます。
## リニューアル構想案(v3)
現状の課題
- ドキュメントがチームに定着しない
- 属人的な引き継ぎによるミス
提案:
- “チームで使えるWiki型ワークスペース”の導入この段階でCursorにこう問いかけます:
「この構想をもっと魅力的に書き直して」
「この案のメリット・デメリットを列挙して」
「似た成功事例は?」
AIが出力した内容を再編集しながら、思考が深まり、構想が具体化していきます。
16:00|Obsidianに再度格納し、「構想→議事録→決定」の流れを可視化
Cursorで構築した資料案は、再びObsidianに貼り戻して、次のようにリンクします。
[[リニューアル構想/Ver3]]
→ [[ミーティング資料/5月28日]] に使用予定
→ [[プロジェクト進行ログ/2025]] に進捗記録このように、「思考の出発点」から「合意」「実行」までがノート上に可視化されることで、“思考の流れ”が再利用可能なナレッジとして蓄積されていくのです。
翌週以降|リンクを辿って“思考の時間旅行”ができる
たとえば、1ヶ月後に次のプロジェクトが立ち上がったとします。
過去のリニューアル構想を参照したいときは、ただこう検索すればいいのです。
[[リニューアル構想/Ver3]]すぐに「なぜそう考えたのか」「誰と議論したのか」「何が決まったか」が分かり、記憶と文脈を取り戻すことができます。
チームに広げるObsidian×Cursorの知的生産文化
〜“個人の知”から“組織の資産”へ〜
前章では、プロダクトマネージャーの1日を通じて、ObsidianとCursorの実践的な活用方法を紹介しました。ここからは、個人で蓄積した知識や思考を、どのようにしてチームに還元し、組織の生産性向上に繋げていくかに焦点を当てていきます。
チームでの情報共有はなぜ続かないのか?
多くの企業で「ナレッジ共有」が課題として挙がりますが、下記のような壁にぶつかることが多いのではないでしょうか?
- ツールがバラバラ(Slack・Notion・Google Driveなど)
- 検索性が悪く、誰も見返さない
- 書くこと自体が業務外の“余計な作業”に感じられる
- “誰が何を考えていたか”が時系列的に追えない
このような問題は、結局のところ「ナレッジが“文脈”ごと共有されていない」ことに起因しています。
そこで鍵になるのが、Obsidianのリンク構造+Cursorによる編集補助という組み合わせです。
Obsidianで「属人知」を“つながる知”へ
個人のノートは、プロジェクト単位やトピック単位で自然とリンクされていきます。
たとえば:
[[プロジェクトX/仕様案]]
→ [[ユーザーインタビュー/4月分]]
→ [[課題分析/導入障壁]]
→ [[スプリント会議/5月15日]]こうすることで、
- 「ある仕様は、どんな背景から生まれたのか?」
- 「過去の議論では何が争点だったか?」
- 「同様の課題は過去にあったか?」
といった**“思考の遡り”や“先行知見の再利用”が一瞬でできるようになります。**
Cursorでチームメンバーの書くハードルを下げる
一方、情報を「まとめる」ことが苦手なメンバーも少なくありません。
そこを補ってくれるのが、CursorのAI編集機能です。
たとえば:
- Slackの雑談ログを貼り付けて、「要点だけまとめて」と依頼
- 議事録の殴り書きを渡して、「議論の論点を抽出して」と依頼
- 曖昧なアイデアに「企画書風に整えて」と依頼
これだけで、“話し言葉→使えるドキュメント”へ昇華できます。
つまり、誰でもナレッジ化の一歩を踏み出せる土壌が整うのです。
「ナレッジの自動回遊」が生む創造性
Obsidianの強みは、手動でリンクを貼らずとも、[[双方向リンク]] や [[バックリンク]] を使って自動的にノートの繋がりが可視化されることです。
すると、「このプロジェクトとあのプロジェクト、実は似た議論していたんだな」「過去の課題と今の課題、根っこは同じだ」といった**“気づき”や“再発見”が自然と生まれます。**
これは、単なるメモアプリではなく、“知のネットワーク”として機能しているからこそ得られる効果です。
社内の「言語化文化」が加速する
こうした活用を日常的に繰り返すことで、次第にチームにも変化が生まれてきます。
- 「この課題、ノートにまとめてあったはず」とリンクを探す文化
- 「言語化しておけば、後で使い回せる」という意識
- 「思考過程ごと共有しよう」という透明性
こうした変化が重なると、ナレッジ共有が“仕組み”ではなく“文化”として根付きます。
Obsidian×Cursorの運用を最適化する実践テクニック
〜テンプレート・タグ・プラグインで加速する知的生産〜
ここまでで、ObsidianとCursorが組み合わさることで、個人の思考がどのように言語化され、チームに共有され、ナレッジとして蓄積されていくかを紹介してきました。
この章では、それらをさらに効率化・高度化するための「運用の工夫」をお伝えします。
テンプレートで“考える土台”を高速で呼び出す
思考をゼロから言語化するのは、エネルギーを要する作業です。
そこで役立つのが、テンプレート機能です。
例:アイデア検討テンプレート
## アイデアの概要
(ここに一文で書く)
## 背景・目的
(なぜそれをやる必要があるのか)
## 想定される価値
- (誰にどんな価値を届けるか)
## 検証方法
- (実験・調査・プロトタイピングの方法)
## 次のアクション
- [ ] 実施タイミング
- [ ] 担当者このようなフォーマットを用意しておけば、Cursorで「このテンプレートに当てはめて」と言うだけで、Slackの会話ログから一発で“整理されたノート”が生成できます。
タグとリンクで“発見性”を最大化する
情報が蓄積されても、使われなければ意味がありません。
そこで重要なのが、発見性を高める設計です。
タグ運用のコツ:
#課題#仮説#検証#施策案のように目的別#PM視点#デザイン思考#ユーザー観察のように思考軸別#2025Q2#新規事業のようにプロジェクト・時期別
リンク設計のコツ:
- ある会議ノートから「関連議論」や「アイデア元」へのリンクを手動で貼る
[[共通タグ]]を通じて横断的に関連性を可視化するDataviewプラグインなどを使って、動的に「この条件に合致するノート一覧」を自動抽出する
プラグイン活用で“思考の支援装置”を増設する
Obsidianの真価は、プラグインによって拡張性が高まる点にあります。
ここでは、知的生産において特に効果的なものを紹介します。
① Templater
変数や日付を動的に扱えるテンプレートエンジン。
「今日の日付+アイデアテンプレ」などが1クリックで生成可能。
② Calendar & Daily Notes
毎日の思考ログを自動で蓄積。過去を振り返る「知的ジャーナリング」が可能。
③ Dataview
ノート間のデータをクエリで抽出・一覧表示できる。
「未着手のタスク」「検証中のアイデア」などをダッシュボード化。
④ Excalidraw
図解とノートをリンク可能。思考の可視化を図と文字で一元管理。
Cursor×Obsidianの「テンプレ化ワークフロー」例
- Slackの会話や会議ログをCursorに貼り付ける
- 「アイデアテンプレートに落とし込んで」と依頼
- CursorがObsidianフォーマットで返してくれる
- それをそのまま
.mdファイルとして保存 - 必要に応じてリンク・タグを補強
この流れを「毎日の業務で自然にやっている」だけで、ストック型の知が増え、あとから再活用されやすくなります。
AI×ナレッジ×マルチツール連携の未来
〜Obsidian×Cursorをハブにした知的ワークスペースの構築〜
ObsidianとCursorの連携は、個人の思考を整理し、チームのナレッジを構築する強力な基盤を提供します。
しかし、現代の知的生産においては、これら2つだけではカバーしきれない領域も存在します。
この章では、「AI」「ナレッジ」「マルチツール連携」という観点から、Obsidian×Cursorを中核に据えた“拡張型ワークスペース”の構想を紹介します。
知的生産の現実:複数ツールに分散する情報
日々の業務で使うツールは多岐に渡ります。
- Slack(チャット・会話ログ)
- Notion(チームドキュメント)
- Google Docs(共有資料・原稿)
- Figma(UI設計・図解)
- JIRA(開発管理)
- Zoom(会議メモ)
これらの情報は、蓄積されてはいるが、“散らばって”いるのが現実です。
この状態を解消する鍵が、**Obsidian×Cursorを中心とした“知識のハブ化”**です。
Obsidianを“情報の最終着地地点”にする
複数ツールの情報を収束させるため、Obsidianを「思考と情報の集積所」として位置づけます。
- Slackで出た会話をCursorで要約し、Obsidianに整理して記録
- Notionでの企画メモを、Markdown形式でエクスポートしリンク付け
- Google Docsのドラフトを構造化して、背景・目的・課題に分解
- JIRAのチケットを参照しながら、検証ログや課題ノートに転記
このように外部情報→構造化→Obsidianへという流れを作ると、思考資産が1か所にまとまり、検索・再利用がしやすくなります。
Cursorの役割:マルチツール間の“意味変換エンジン”
Cursorの真価は、ツールの間を“意味”でつなぐ変換器になれる点です。
具体例:
- Slackのやりとり → 「仕様検討メモ」に変換
- Google Docsの文章 → 「プロジェクトの背景」に要約
- Zoom文字起こし → 「議論の要点」リストに再構成
- FigmaのURL+文脈 → 「UIの意図と改善案」に転写
これにより、ツールごとに異なる情報のフォーマットが、「Obsidianに適した構造」に自然に整理されていきます。
ZapierやMakeとの連携で、ノイズを削ぎ落とした自動化も可能に
Cursorの生成結果をもとに、ZapierやMakeなどのノーコード自動化ツールを使えば、
- 指定のフォルダに入れたMarkdownファイルを自動でObsidianに取り込む
- タグに応じてカテゴリ分けされたノート一覧を自動生成
- チームで共有した議事録の要約を、週報形式でメール配信
など、知的作業の補助的部分を無人化=思考に集中できる環境を作れます。
Obsidian×Cursorを中心とした“知的生産エコシステム”
最後に、筆者が実践している連携例を紹介します。
Slack → Cursor → Obsidian(会話ログの要約・記録)
Zoom → Otter.ai → Cursor → Obsidian(議事録の生成)
Notion → Obsidian(プロジェクトノートのアーカイブ)
JIRA → Cursor → Obsidian(進捗と課題の記録) これにより、すべての知的活動が“1つの場所”に蓄積され、時間を超えて再利用できるナレッジ資産となっていきます。
AI伴走型の知的生産へ 〜未来の働き方をObsidian×Cursorで先取りする〜
テクノロジーの進化により、「書く」「考える」「記録する」「共有する」といった知的作業の形は、いま大きく変わりつつあります。その中心にあるのが、「AIと共に働く」という考え方です。
この章では、Obsidian×Cursorを活用した“AI伴走型”の知的生産スタイルを振り返りながら、これからの働き方について提言します。
なぜ今、“AI伴走”が重要なのか?
人間の知的リソースは有限です。
- 毎回ゼロから考える時間
- 過去に書いた内容を探す時間
- 情報を整理して伝える時間
これらはすべて、「価値ある仕事」ではあるけれど、「もっと短くできる仕事」でもあります。
AIは、あなたの“第2の頭脳”として、**単なる補助ではなく「共に思考するパートナー」**になりつつあります。
Obsidian×Cursorがもたらす“知的ループ”
本連載で紹介した2つのツールには、それぞれ異なる役割がありました。
- Obsidian:思考の記録・構造化・蓄積
- Cursor:情報の生成・整理・変換
この2つを組み合わせることで、次のような知的ループが成立します。
- 思考をメモ → Obsidianへ
- 課題や疑問を抽出 → Cursorで深掘り
- 新しいアウトプットを生成 → さらにObsidianに記録
- つながりが生まれ、知識が体系化される
つまり、AIとの対話を通じて、自分の中にある断片的な思考が「体系化された知」へと進化していくのです。
“思考が蓄積する”環境が、働き方を変える
この知的ループが日常的に機能すれば、次のような変化が起きます。
- 会議で「何を話していたか?」を思い出す時間がゼロに
- 過去の議事録を検索すれば、必要な文脈がすぐ見つかる
- 自分の思考ログを読み返すことで、自己学習が加速する
- 新人メンバーが「蓄積された思考」を学習できる
これは、単なる効率化ではなく、組織や個人の“ナレッジ・インフラ”の変革と言えるでしょう。
プロダクトマネージャーにこそ必要な「知の再利用性」
筆者はPM(プロダクトマネージャー)として多くの判断とコミュニケーションを担っています。
その中で感じるのは、「一度考えたことを、何度も思い出す時間」がいかに無駄か、ということ。
- 「あの時なぜこの設計にしたんだっけ?」
- 「ユーザー要望の背景ってなんだった?」
- 「上司に説明したロジック、再利用できないか?」
Obsidian×Cursorを活用すれば、過去の思考・議論・意思決定のログがすべて資産化され、再利用可能になります。
これは、PMだけでなく、あらゆる知的職業にとって“働き方のアップグレード”になるはずです。
まとめ:知的生産の“当たり前”が変わるとき
この連載を通じてお伝えしたかったことは、以下の3点に集約されます。
- Obsidian×Cursorは、現代の知的作業に最適化されたツールである
- AIを「使う」ではなく「共に考える」存在として捉えるべきである
- 思考を記録し、再利用する文化が、これからの差を生む
これまで属人的だった「考え方」や「判断の流れ」が、構造化され、共有され、受け継がれていく。
そんな未来の知的生産を、いまから構築してみませんか?
おわりに:未来のあなたへ手渡す“思考の資産”
AIと共に働くことが当たり前になった時代、真に価値を持つのは「人間の問い」や「思考の深さ」です。
Obsidian×Cursorを使いこなすということは、未来の自分へ“知の遺産”を手渡すことに他なりません。
明日の議論も、来週の企画も、5年後の新人育成も、
すべて“いまのあなたの思考”が土台になります。
ぜひ、今日からその一歩を踏み出してみてください。






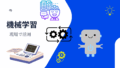
コメント