
「プログラマーやめとけって聞くけど、実際どうなの?」
このような疑問にお答えします。
プログラマーについて検索すると、「プログラマーやめとけ」ってよく出てきます。
結論から言うと、プログラマーはおすすめです。その理由についても解説していきます。
「未経験 プログラマー やめとけ」が検索ヒットする理由とその背景
なぜ今、「プログラマー やめとけ」が検索されているのか?
近年、このようなキーワードを頻繁に目に入るようになりました。
特に未経験からプログラマーを目指そうとする人にとっては、不安を煽られる内容ばかりで「本当に自分でもなれるの?」と足踏みしてしまう人も多いはずです。
では、なぜこのようなネガティブな言葉が拡散されているのでしょうか?
SNS時代の「ネガティブ投稿」は伸びやすい
まず前提として、ネガティブな情報ほど拡散されやすいというSNSの特性があります。
「つらい」「辞めたい」「後悔した」などの感情を含んだ投稿は共感を生みやすく、X(旧Twitter)やYouTubeでもインプレッションが伸びやすい傾向にあります。
つまり、「やめとけ」という投稿が多く目に入るのは、単にバズりやすいからという理由もあるのです。実際に業界全体がブラックかというと、それはまた別の話になります。
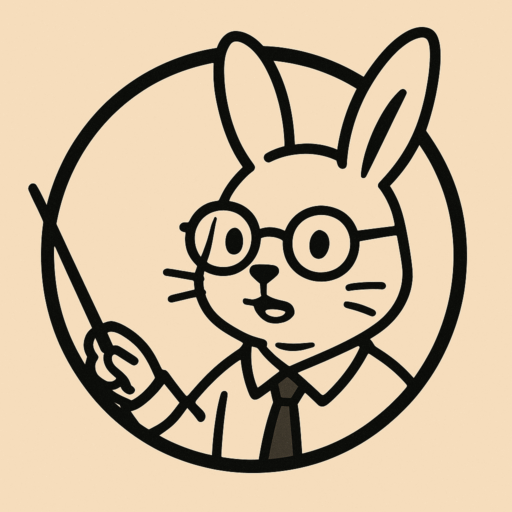
「プログラマーに限らず、他の職種も”やめとけ”ってよく出てくるよ」
「やめとけ」には2種類ある
よくある「やめとけ」投稿には、大きく2つのタイプがあります。
1つは、本当に劣悪な環境で働いた経験者の体験談
ブラック企業に入社して、無理な納期や残業に苦しみ、やむなく退職した人が書いたケースです。
もう1つは、学習の初期段階でつまずいて挫折した人の投稿
「思ったより難しくて挫折した」「全然わからなくて自信をなくした」など、挑戦の入り口で感じたつらさからの発信です。
このどちらも、決して無視できないリアルではありますが、それが業界全体の真実とは限りません。
誰にとって「やめとけ」だったのか?
たとえば、「プログラマーは残業が多くてつらい」という声がある一方で、「リモートで柔軟に働けて快適」と語る人もいます。
この違いは何かと言えば、どの会社を選んだか、どんな働き方を望んだかにかかっています。
つまり、重要なのは「未経験者がやめとけかどうか」ではなく、その人にとって“合った環境”を選べていたかどうかなのです。
未経験でプログラマーを目指すことは無謀なのか?
「やめとけ」という言葉が流行っている今、挑戦をやめてしまうのはもったいないことです。
実際には、未経験からでもエンジニアになって活躍している人は多数存在します。文系出身・30代・主婦・異業種からの転職など、さまざまなバックグラウンドの人たちが、学習と努力を重ねてエンジニアとして活躍しています。
結論から言えば、「やめとけ」がすべての人に当てはまるわけではないのです。
「やめとけ」は本当か?現場のリアルと誤解の正体
「プログラマーはブラック」は真実か?
ネットやSNSでは、「プログラマーは地獄」「納期がやばい」「休日もコードを書いてる」など、まるで業界全体がブラックかのような声が散見されます。
確かに一部の企業や案件では、過重労働やスケジュールの無理な押し込みがあることも事実です。しかし、それが業界の標準ではありません。
実際に働いているエンジニアの中には、「定時で退社して副業もしている」「フルリモートで地方から働いている」「残業ゼロでプライベートが充実している」と語る人も大勢います。
つまり、「どこで働くか」「どんな仕事を選ぶか」で環境は大きく異なり、すべての会社がブラックなわけではないのです。
「実力社会」は怖い?
プログラマーの世界は、実力が問われる職業であることは間違いありません。年齢や肩書きよりも、「何を作れるか」「どう動けるか」が評価に直結します。
そのため、「学歴や職歴に自信がない」という人にとっては、むしろ実力社会のほうがチャンスがあるとも言えます。
一方で、スキルが追いつかないと不安に感じることもあります。これが「向いてない」と思わせる原因のひとつですが、裏を返せば、勉強を継続できれば、誰にでも扉が開かれている業界なのです。
未経験がつまずく“3つの落とし穴”
実際に「プログラマーやめとけ」となる人が陥りがちなポイントがあります。
1. 完璧主義で進まない
「コードを1行書くのにも何時間も悩む」など、完璧を求めすぎる人は挫折しやすいです。まずは動くものを作り、あとから改善するマインドが大切です。
2. 孤独に抱え込みすぎる
独学で黙々と取り組むのは美徳にも見えますが、悩んだら誰かに聞く・コミュニティに参加するという「開かれた学び」が続ける鍵になります。
3. 転職先の選び方を間違える
SESや受託開発企業など、未経験OKでも業務内容や環境に差が大きいため、「最初の職場選び」は慎重に。求人内容と実態の差に注意しましょう。
エンジニア業界は“選べる”時代に
ITエンジニアの働き方は、年々多様化しています。リモートワーク、副業OK、フレックスタイム制など、柔軟な環境を整える企業が増えています。
さらに、クラウドソーシングやフリーランスの案件も増加しており、「会社に属さなくても収入を得られる」道も現実味を帯びています。
重要なのは、「業界」ではなく「あなたが働く場所と働き方」です。無理な環境で我慢する時代は終わり、自分の価値観に合った働き方を選べるのが、現代のエンジニアの魅力です。
「やめとけ」は一面の真実。でも、それだけじゃない
プログラマーの仕事は、確かに楽ではありません。学び続ける姿勢、柔軟な思考、そして成長意欲が必要です。
しかし、それが「つらいだけの仕事」かと言えば、決してそうではありません。モノづくりの面白さ、ユーザーに価値を届ける喜び、時間や場所にとらわれない働き方…。その先には確かなやりがいがあります。
それでもプログラマーをおすすめする5つの理由
「やめとけ」と言われることも多いプログラマーですが、現場で働いているエンジニアの多くが実は口を揃えてこう言います。
「大変だけど、やっぱりプログラマーになってよかった」と。
ここでは、未経験からでもプログラマーをおすすめする「確かな理由」を5つに絞ってご紹介します。
理由1:将来性が圧倒的にある
IT業界は今後も成長が見込まれている数少ない分野です。AI、IoT、Web3、SaaS、ロボティクスなど、新しい技術の進化にともない、開発者の需要はますます高まっています。
経済産業省のレポートによれば、2030年には最大79万人のIT人材不足が予測されています。つまり、しっかりスキルを身につければ、就職・転職に困らないどころか、引く手あまたになる可能性があるのです。
理由2:学歴・職歴に縛られない“実力主義”
他の職種では「大企業に入るには学歴が必須」「文系だと不利」といった壁がありますが、プログラマーの世界では**「何が作れるか」が評価の基準**になります。
実際に、高卒・フリーターからスタートして、大手企業に転職したり、フリーランスで年収を上げたりする人も多数存在します。
これは、実績がポートフォリオやGitHubなどで“見える化”されやすい職種だからこそできること。年齢や経歴よりも「自分で学んで動ける人」が強い業界です。
理由3:場所に縛られず働ける自由さ
2020年以降、急激に普及したのがリモートワークです。プログラマーはパソコンさえあればどこでも働けるため、地方在住・子育て中・海外在住のエンジニアも増えています。
通勤ストレスがない、住む場所を自由に選べる、働く時間も柔軟――。これはオフィスワークではなかなか得られない大きなメリットです。
会社員として働きつつ、副業やフリーランスにシフトしていく人も多く、働き方の多様性を実現しやすい職業と言えるでしょう。
理由4:ものづくりの喜びがある
プログラマーの仕事の本質は、「問題解決」と「ものづくり」です。自分のコードでアプリが動き、誰かの課題が解決されたときの達成感は格別です。
「自分が作ったサービスがユーザーに喜ばれる」
「バグを潰して正常に動いた瞬間のスカッと感」
「仲間とチーム開発して完成させたときの一体感」
技術の習得は確かに地道ですが、その先にあるやりがいや達成感は非常に大きいのです。これを味わうと、「大変だけど楽しい」「やっぱり辞めたくない」と感じる人が多いのも納得です。
理由5:副業・独立のチャンスが広がる
スキルを身につけた先にあるのが、収入や働き方の自由度です。プログラマーは個人で受託開発をしたり、Webサイトを請け負ったり、技術ブログで収益化するなど、スキルが収入に直結するチャンスが豊富です。
実際に、平日は会社員、夜は副業エンジニアという働き方をしている人もいれば、フリーランスで月収50万〜100万円超の案件を複数掛け持ちする人もいます。
このように、自分次第で未来を切り開けるのが、エンジニアの強みなのです。
「やめとけ」の声よりも、自分の可能性を信じよう
たしかにエンジニアの道は楽ではありません。覚えることも多く、トライ&エラーの繰り返しです。けれど、だからこそ面白い、だからこそ成長できるという側面も持っています。
「つらい」の先にあるものを、自分の手でつかみ取る。その挑戦に、プログラマーという選択肢は価値あるものになるはずです。
未経験でも失敗しない学習ステップと、最初の一歩の踏み出し方
「何から始めればいいの?」と迷ったときは
プログラマーに興味を持っても、最初の一歩で立ち止まってしまう人は少なくありません。
「どの言語がいいのか分からない」「何を目指せばいいのか分からない」――そんな迷いを抱える人こそ、“手を動かすこと”から始めてみてください。
大事なのは、完璧な計画よりも、行動してみること。ほんの数時間でも手を動かしてみることで、学ぶべきことが具体的に見えてきます。
未経験者向け:最短でプログラマーになるための学習ステップ
未経験でも効率的にプログラマーを目指すには、次のような学習ルートが有効です。
1. HTML/CSSの基本を覚える(1〜2週間)
まずは「Webページの骨組み」と「装飾」を学びます。
YouTubeやProgateなどの無料教材を使って、簡単な1ページサイトを作ってみるのがおすすめです。
2. JavaScriptでページに動きをつける(2〜3週間)
「ボタンを押したら画像が変わる」「入力値を表示する」といった簡単な動きを学びましょう。
この段階で「コードを動かす楽しさ」を実感できます。
3. Git/GitHubを使ってコードを管理する(1週間)
プログラマーとしての基本ツールであるGitとGitHubの使い方も習得しておきましょう。ポートフォリオを作る際にも必須のスキルです。
4. Reactなどのフレームワークに挑戦(1〜2ヶ月)
就職・転職市場で人気が高いのがReactやVueといったJavaScriptフレームワークです。これらを使って、ToDoアプリやチャット風UIなどを作ってみると、実務に近い開発が体験できます。
5. 自分のポートフォリオを作って公開(1ヶ月)
これまで作った作品をひとまとめにし、自分のスキルをアピールするためのポートフォリオサイトを作りましょう。
自分の学びや考えも添えることで、採用担当者の目にも留まりやすくなります。
独学?スクール?どちらを選ぶべき?
学習の方法として、「独学かスクールか」で悩む方も多いでしょう。それぞれの特徴は以下の通りです。
- 独学:コストを抑えられる/自由なペース/継続が難しい
- スクール:効率的に学べる/就職サポートあり/費用がかかる
おすすめは、「最初の1〜2ヶ月は独学 → 伸び悩んだらスクール検討」という流れです。
最初から高額な投資をするよりも、自分に向いているか試しながら判断するのがリスクが低くて現実的です。
失敗しないための3つの心構え
- 完璧を求めすぎない
最初は分からなくて当然。動けばOK、後で改善すればいい。 - 小さく作って公開する
最初のうちはミニアプリでも大丈夫。大切なのは「アウトプットすること」。 - 1人で抱え込まない
学習仲間を見つける、SNSで発信する、誰かに聞ける環境を作るのも継続のコツです。
🎯 まとめ:やめとけの裏にある“本当の価値”を見逃さないで
- 「やめとけ」は一部の声であって、業界全体を表してはいない
- ITエンジニアは将来性が高く、実力次第で自由度の高い働き方ができる
- 未経験からでも手を動かし、ステップを踏めば誰でもチャンスがある
- 大切なのは、正しい順序とマインドセット、そして継続する仕組み







コメント